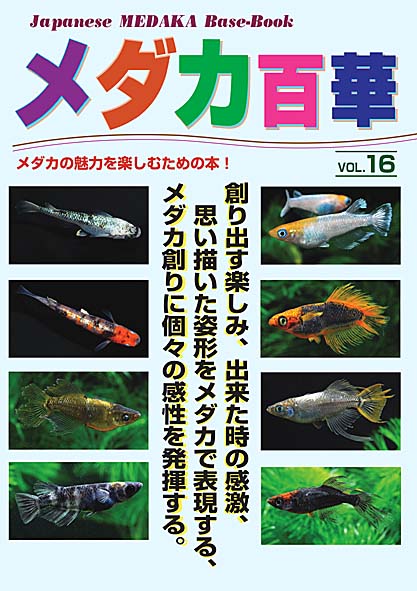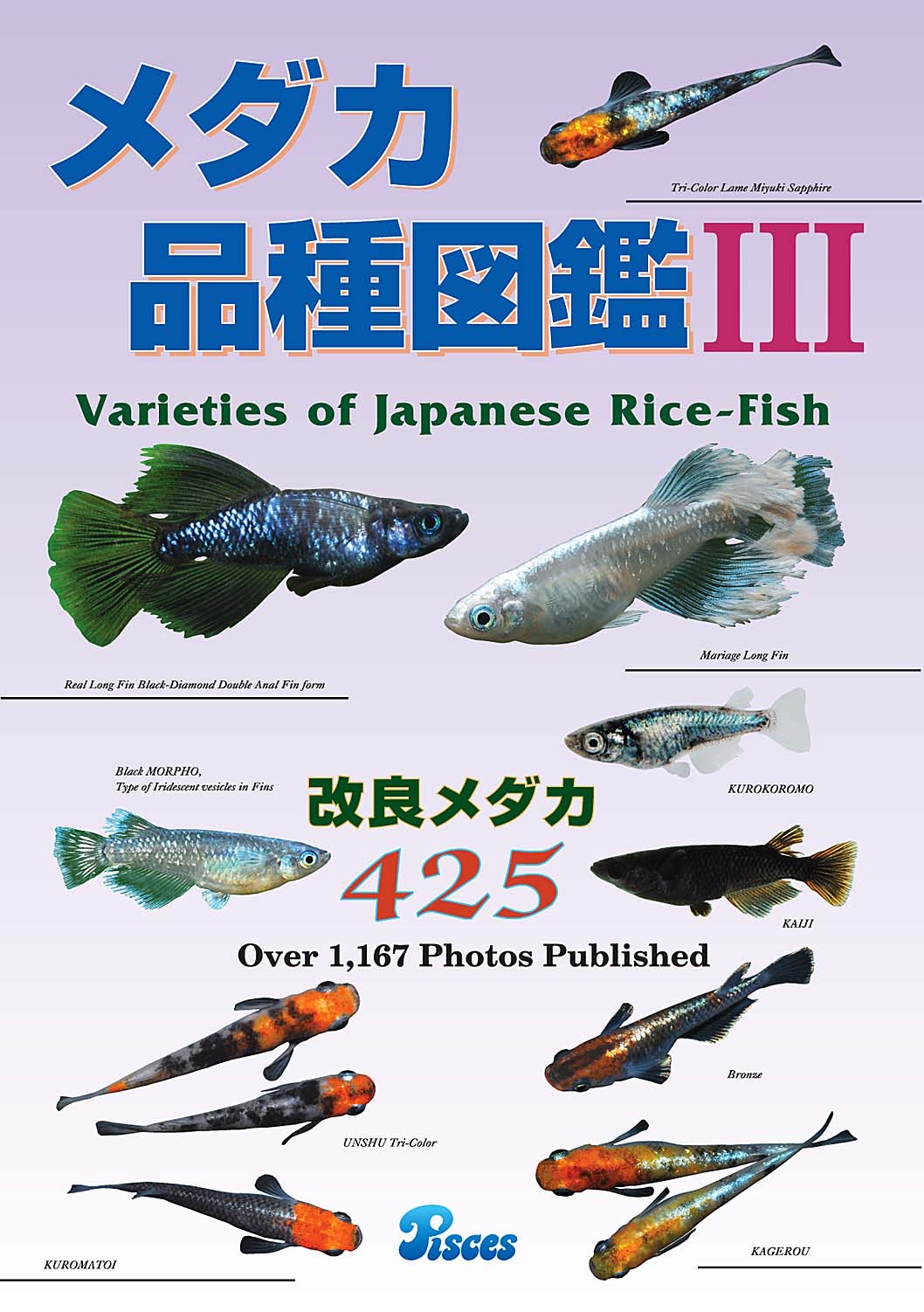日本の水草 コウホネ
コウホネはスイレン科の抽水植物で、北海道から本州、四国、九州、朝鮮半島と広く分布する。
地中に太い茎を伸ばして殖えていき、その地下茎が白っぽいことから骨を連想させ、漢字では“河骨”と書かれる。アクアリウムでは15cmほどの葉を持つ小株が古くから販売されている。

緩くウエーブのかかった明るい緑の水中葉は繊細な美しさを見せるが、栽培には十分な日照が必要なため、室内の水槽などでは強光量の照明設備が必要になるので、屋外栽培向きと言える。
溜め池や湖沼などで繁茂する姿が観察できる。

30cmを超える矢尻型の大きな葉を水上に出しており、水中葉とはまったく異なる印象を受ける。
水中葉は水深にもよるが、水面に到達して浮き葉になる。その間から黄色い花が見えていた。

環境によって水中葉のままであったり、水上にでる抽水葉であったりと、様々な姿を見せる。

ここでは、岸近くには浮き葉や花が見えていたが、奥は大型の抽水葉で埋め尽くされていた。
ふと気づくと、花の色が赤っぽいものも見られた。

コウホネの栽培品種には、花が赤いベニコウホネがある。どうやら混成しているようであった。この池は、以前にはコウホネは見られなかった。その後、護岸改修や清掃が行われ、コウホネが植栽されたのだろう。