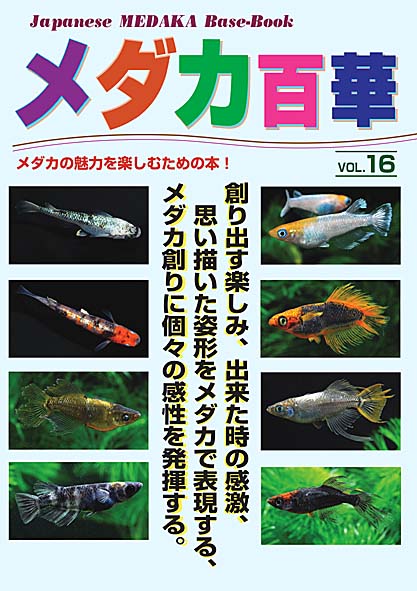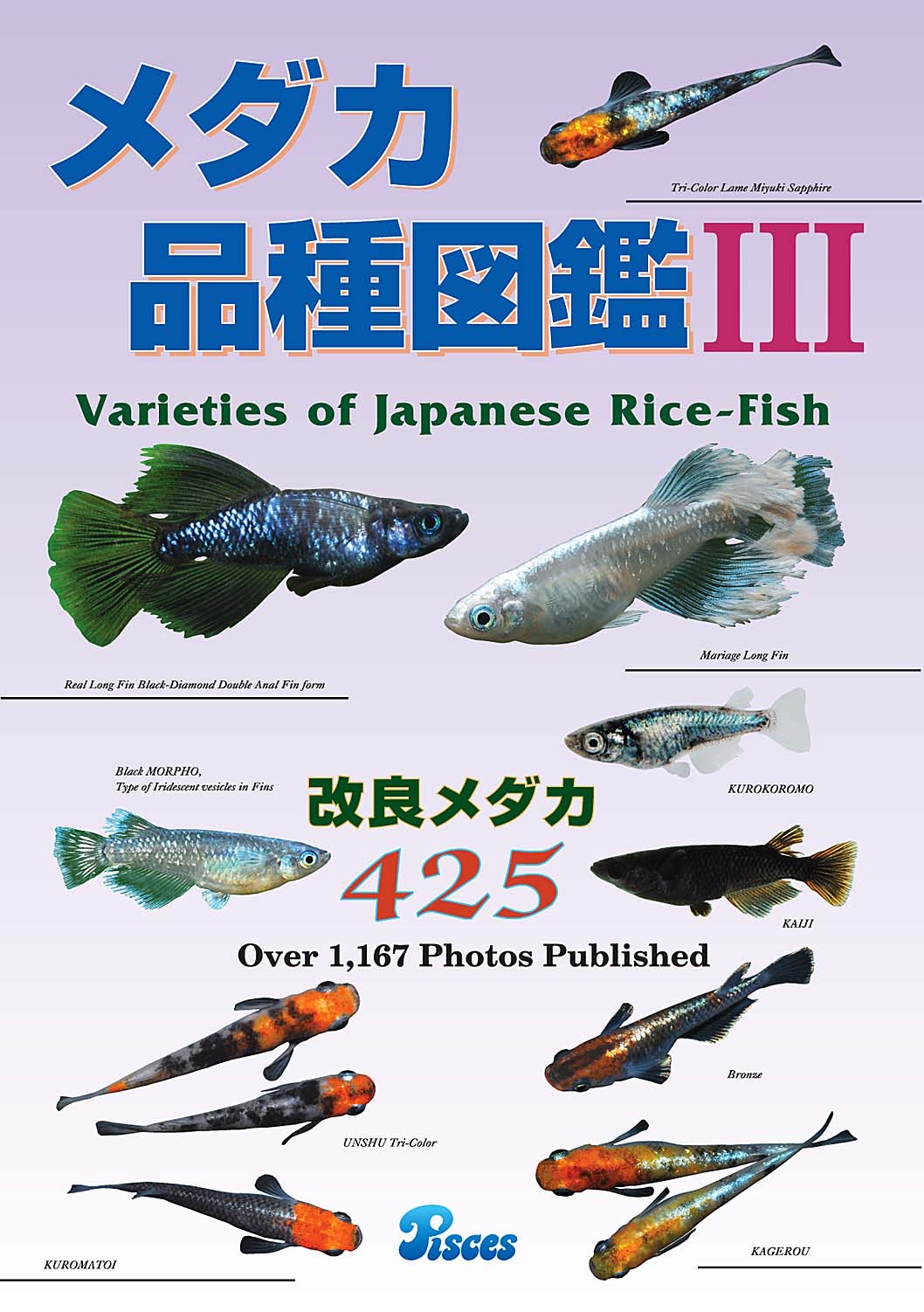食虫植物 イシモチソウ
突然の雷に豪雨、時には雹が降ったりといった不安定な天候ではあるが、季節は確実に進み、植物の生長も徐々に進んでいる。春の湿原では、食虫植物も動き出していた。

こちらは成東・東金食虫植物群落。大正9年に天然記念物に指定された湿原で、湿性植物や食虫植物が見られる。近年では周辺の田んぼの減少による水の不足や、それに伴い川から水を供給したことでの富栄養化によってススキなどの大型植物の繁茂などもあるそうで、守る会などのボランティア活動などによって保護活動も行われている。

人が勝手に立ち入れないようになっているからこそ、こうした環境が守られているという部分もある。
まずはイシモチソウ

食虫植物であるモウセンゴケの仲間。他のモウセンゴケと違って茎が直立する姿が特徴的である。時期始めのためか、まだ高さは10cmに満たない程度であったが、育つと20cmほどになるという。そうなればかなり見応えがありそうである。
葉に付いている腺毛から出る粘液で昆虫などを絡め取る。

この粘液の粘着質が強く、小石でも持ち上げてしまうことが名前の由来になっている。そこまで強いのか?とも思えるが、光る粘液の粒は美しい。
こちらはコモウセンゴケ

イシモチソウよりも盛期は遅いので、まだ株が芽吹いてから間もないようで、下草の間に1cmほどの小さな株がひっそりと開いていた。
この後、6月くらいでイシモチソウのシーズンは終わるが、夏前にはコモウセンゴケやナガバノイシモチソウが、そして夏にはミミカキグサの仲間が見られるようになる。
最も目についたのはハルリンドウ

澄んだ青紫の花弁が湿原の彩りになっていた。この花は日が出ていないと咲かないそうで、日が陰っていたり、夕方になると閉じてしまう。この日も午後からは不安定な天候になっていたので、午前中の観察で助かったものであった。

葉はごく小さく、ロゼット状に花をつける。この株は10輪以上の花をつけており、見事な姿であった。
トキソウ

鳥のトキを思わせる色合いをした湿地性の蘭の仲間。蘭といってもそのサイズはごく小さく、この花で2cmもない。しかも近くにはないのはお約束。時期的には少し早いようで、生長途中のつぼみを付けた株が多数見られた。もう少し後であれば、見事な群落が見られそうであった。
最後に見られたのはショウブ

湿地などに見られる抽水植物で、葉は独特な香りがする。折りしも端午の節句。風呂に菖蒲の葉を浮かべるが、さすがにスーパーなどで売られているものと比べると葉は小さかった。

花の集まった花序も見られた。
この後も季節によってさまざまな湿性植物が見られる場所である。季節ごとに訪れてみると、その時期ごとの出会いがありそうであった。