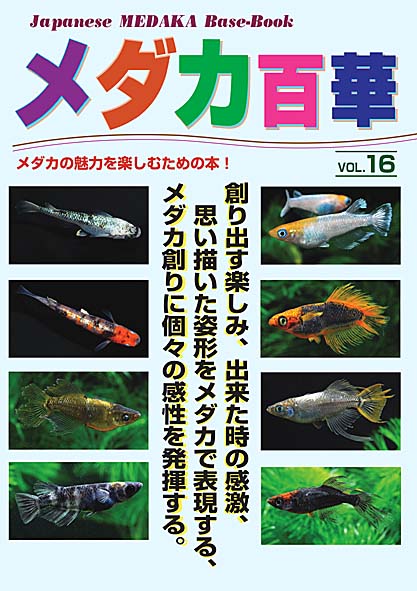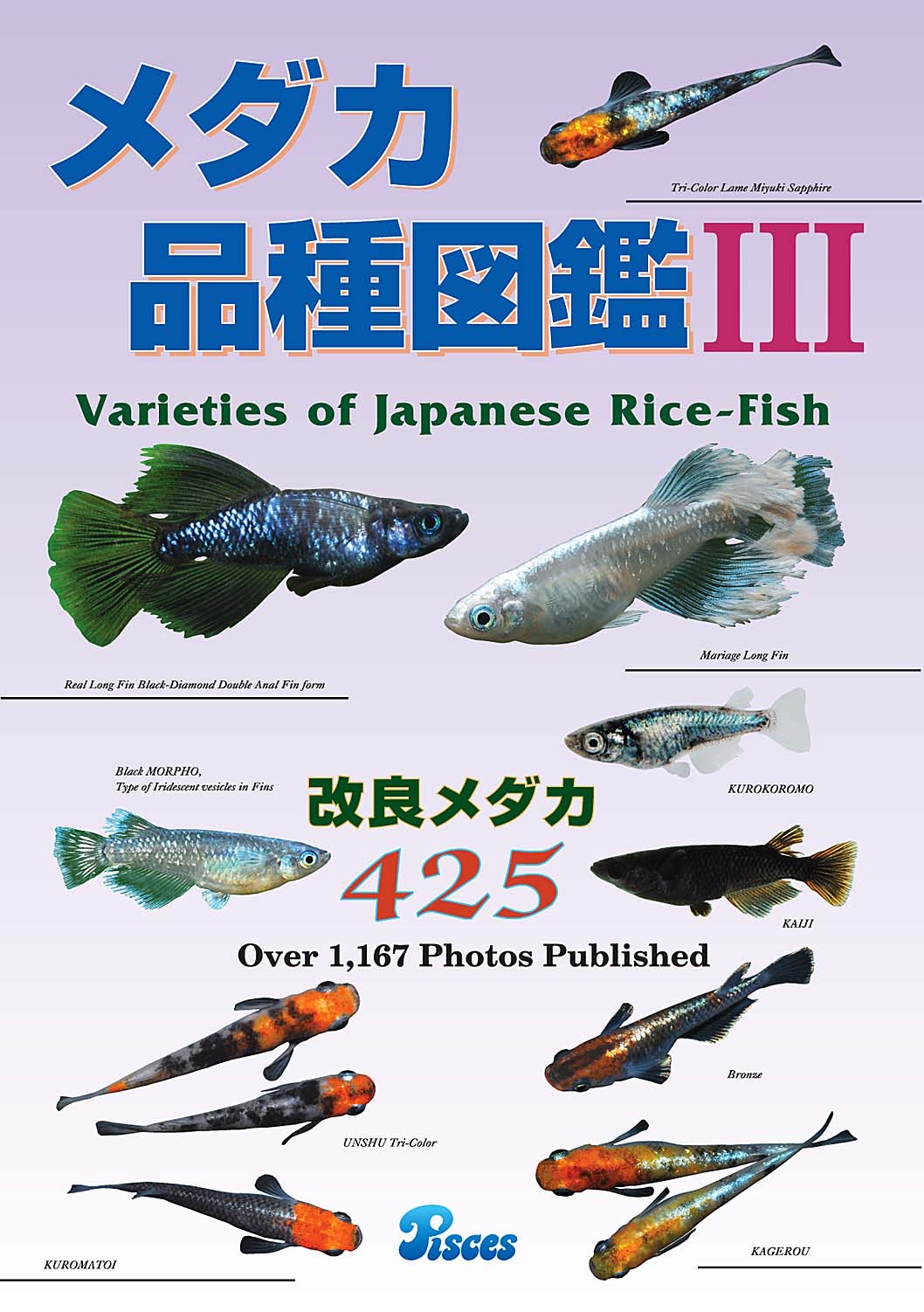溢れる水への対処
飼っているメダカが殖えたり、新たな品種を導入したりと、メダカの飼育容器はだんだんと増えていく。最初こそは軒下などに置いていたが、数が増えてくると空きスペースを見つけて詰めていくようになった。軒下ならば、ある程度の雨が降っても問題ないのだが、場所によっては雨ざらしになることも少なくない。

春の長雨とも呼ばれるこの時期のぐずついた天候だが、先日に降った雨は叩きつけるような強烈な降りで、しかも延々と降り続いた。こうなると直接雨の入る容器の水はあっという間に溢れてしまう。メダカたちも深い場所へ移動したりもするが、稚魚などは水の流れと共に外へ流されてしまうこともある。あらかじめ雨が降ることがわかっていれば、水位を下げておいたり、蓋になるようなものを用意しておけばよいが、思った以上の降りだったりすると、蓋を伝って入る雨で溢れてしまうこともある。
そんな状況への対処がいくつかある。よく見かけるのは、容器の縁にスポンジや布など水を通す素材を挟むやり方である。

これは毛細管現象やサイフォンの原理といった単語を理科の授業などでも聞いたことがあるだろう。水の表面張力や管などを通して水を導く現象を利用している。容器内側の位置よりも外側が低くなるようにスポンジを固定すると、容器内の水は溢れる前にスポンジを伝って染み出し、スポンジの位置で水位を保つことができる。

やり方は人それぞれである。洗濯ばさみで固定したり、穴を使ってそこに固定したりと、いろいろ試してみるとよいだろう。
発泡スチロールの容器で、一部分を切り取って網を挟み込んでいる。

網目の大きさを調節することで、稚魚から親魚まで対処できる。じわじわと染み出すスポンジなどに対し、こちらはもっと直接的に水が流れ出る形である。
メダカ用の発泡製製品では、水抜き用の穴が設けてあるものもある。

そこへウールなどを詰めることで、魚が流れ出さないように工夫されていた。
こちらはサイフォンの原理を用いたもの。たらいに穴を開けてホースを通している。

ホースの位置以上に水位が上がらないようにできている。ホースの経ではメダカも出てしまうので、容器内のホースの先には網などをセットしておく。
ちょっと手間と工作作業が必要になるが、オーバーフロー方式もある。

パイプなどを立て、水位が上がり、その高さまでいくと溢れる仕組みである。容器に穴を開けたり、パイプの高さ調整、魚が流れていかないようにするなどの工作が必要だが、これができていれば、一方から水を少しずつ流すようにすると、常に少量ずつ水が流れていくことになり、水質悪化を軽減できたりもする。
いずれにしても、急激な大量の雨では許容量を超えてしまうこともあるので、強い降りの場合はしっかりと観察しておきたい。通常の雨であれば、こうした対処をしておけば、慌てなくても済むものである。